| 人口:19,644人 高齢化率:18.9% 保健師数:3名 | |
| 岩舟町では,平成元年に第一次予防を目的とする「いきいき岩舟推進プラン(健康づくり10ヶ年計画)」を策定しました。しかし,この計画は行政主導でまとめられたものであること,また,評価方法が確立していなかったため,10ヶ年の実績の把握が困難であり,保健計画の見直しの必要に迫られていました。 そこで,この度,平成11年〜12年度に地域保健推進特別事業を受け,「健康日本21地方計画」(第二期いきいき岩舟推進プラン)を策定しました。 |
||
| これまでの「いきいき岩舟推進プラン」は,行政主導でまとめられたものであり,住民は受け身となっていました。しかし,健康な地域づくりを推進するためには,住民自らが目標を決め,その方法までも考えていく,つまり,住民が計画の策定から評価まで関わることが大切と考えました。 この点を踏まえ,「第二期いきいき岩舟推進プラン」の策定では,プラン策定の必要性,新しい健康づくりの考え方,目標,施策の方向性,事業計画について,段階別に住民や多くの職員との間に共通理解を深めていきました。 |
||
| 1) | 保健課職員,町職員の研修会 保健課職員,町職員の「計画づくりをしよう」という意識を高めた。 |
|
| 2) | 健康ボランティア(けんこう普及員の会)の交流 現在の活動に行き詰まり感があったため,今後の活動の方向性について見直した。 |
|
| 3) | 住民と健康ボランティアの交流 健康ボランティアが中心となり,住民の健康づくりへの思いや夢,希望等について話し合った。 |
|
| 4) | 同世代グループ内での交流 同世代の人達の思いを,互いに語り合った。 |
|
| 5) | 異世代の人との交流 異世代の人達の思いを,互いに語り合った。 |
|
| 6) | 推進委員会の開催 県南健康福祉センター,栃木健康福祉センター,都立大学,自治医科大学,町医師会・歯科医師会,町が,町の現状や課題について話し合った。 |
|
| 1) | 既存資料から地域特性や健康問題,社会資源を把握した。 (1)係全員で,町の各課,教育委員会,県南健康福祉センター,歯の健康センター,国保連合会等から情報を収集 (2)業者に委託して経年変化や他地域との比較を図表化してもらった。 |
|
| 2) | 町民の意識調査 |
|
| 1) | 健康づくりシンポジウムの開催 下記の要領で「健康づくりシンポジウム」を開催し,各世代から健康づくりについての提言を得ることができました。 日 時 平成12年2月20日(日) 午後1時〜3時 会 場 岩舟町文化会館大ホール テーマ 「町民だれもが健康で安心して,いきいきと暮らせるまちづくり」 内 容 ○健康づくり報告 いきいき岩舟推進プラン(健康づくり推進10か年計画)を終えて ○シンポジウム 「第二期いきいき岩舟推進プラン」健康づくりを考える 〜各世代からの提言〜 |
||
|
|||
| 2) | 庁内連絡会議の開催 町民が描いている「健康に暮らすためのまち」を築いていくためには,行政間における相互の情報交換,施策や事業の見直し,連携による効率化を進める必要性が生じてきました。 そこで, (1)「第二期いきいき岩舟推進プラン策定事業」の概要説明と,ヘルスプロモーションについての理解を深めた。 (2)町の現状や課題と,町民の夢や希望に沿った施策アイディアを募集した。 (3)現在の施策の紹介をしてもらった。 上記(1)(2)(3)の事から,住民の夢や希望と,担当者の問題意識が一致することが分かりました。 |
||
| 3) | 健康なまちづくりの先進地との交流会 長野県須坂市,群馬県下仁田町との交流会は,施策の方向性や事業計画検討材料として参考になりました。 (1)長野県須坂市 ボランティアの活性化策や地域単位での自主活動を学びました。 (2)群馬県下仁田町 歯科保健の取り組みや健康サークル活動について学びました。 |
||
| 4) | 講演会の開催 「こころの健康づくり」というテーマで講演会を開催しました。 |
||
| 1) | 庁内連絡会 町の現状や課題を知った上で,担当課・団体としては何ができるのかの提案を得た。 |
||
| 2) | 健康づくり推進協議会の開催 |
||
| 岩舟町においては,保健師がリーダー,つまり中心的な立場で計画策定を進めることができました。 | ||
| 「岩舟町健康づくり推進協議会」を策定委員会として組織しました。 | ||
|
||
| 推進協議会の委員として住民の参加を得ることができました。特に健康ボランティアの方々が中心となり,足を使って住民の声を拾ってくれました。そして,その内容をシンポジウムで発表するという形式をとりました。これが,住民の考えや意見を計画に反映させる上でおおいに役立ちました。 また,計画策定を通して,これまで接点や関わりの少なかった町内の他課や町外の機関と連絡をとるようになり,相互に町の現状について話し合うことができました。 |
||
| 岩舟町では,町独自の柱を設定しました。 | ||
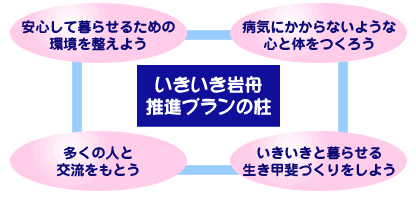 |
||
|
○健康づくりを支える基盤の整備と推進体制の強化 ○人の移動が保証される交通環境や道路の整備,公共施設への安全なアクセスの確保 ○医療・保健制度の活用 ○地域社会の構成員である人と人とのつながりを深めていこう ○すべての町民の自己実現・自己決定を保障する基礎となる情報提供・入手・発信体制を作ろう ○健康情報の提供システム ○救急医療体制の充実 |
||
|
○感染症予防対策を徹底しよう ○積極的に健診を受け,自己の責任のもとに健康管理をしていこう ○健康的な生活習慣を身につけるなど健康づくりを楽しもう ○精神障害の発症を予防し,積極的なこころの健康づくりをすすめる ○生涯にわたって,自分の歯で自由に食を楽しめるような歯の健康づくり ○現在ある健康づくりの地区組織間の交流を深め,地域に浸透させていく |
||
|
○世代間交流の場を多くもって,地域の中でコミュニケーションを増やしていこう ○仲間づくりを進めていく場を提供していこう ○交流の拠点となるような,公共施設の場を確保する ○現在ある健康づくりの地区組織間の交流を深め,地域に浸透させていく |
||
|
○地域の中で健康づくりを楽しむ自主グループへの支援 ○寝たきりであっても生きがいのもてるような支援 |
||
| 健康づくりの各地区組織同士が活動についての情報交換を行う事で,各組織活動の課題が解決され,新しい活動が生み出される。 | ||
| 1. | 子育てに関する組織の交流→10年後に活動の報告会 育児サークル,母子保健推進員,児童民生委員,家庭教育オピニオンリーダー,更正保護婦人会,社会福祉協議会,障害児者父母の会,行政関係者 |
|
| 2. | 成人の健康増進に関する組織の交流 健康普及員の会,農協,商工会,社会体育指導員,地区社協,老人クラブ連合会,保健委員,行政など |
|
| 大学などの研究機関に所属する有識者として,都立大教授の星旦二先生と自治医科大学教授の中村好一先生のご協力を得ることができました。 | ||
新しい健康づくりの考え方(ヘルスプロモーション活動の重要性とそのメリット)を町の実態に合わせて説明していただきました。また,いきいきと暮らせるためのモデル的な情報や意見の提供などの協力をしていただきました。 |
||
統計に関する助言(既存データの扱い方,データの読み方)や高齢者生活調査への支援,数値目標の扱い方について助言していただきました。 |
||
| 厚生省(現厚生労働省)の目標値と,住民調査の結果を参考に設定しました。 | |
| ○町の団体・ボランティア・社協・他課が,それぞれ自分の役割に問題意識をもつようになりました。 ○健康に暮らせる町を作るために,住民自らが行動できるよう,環境を整備していくことの重要性を再認識しました。 ○栃木県衛生年報,生活実態調査,国保連合会疾患分類統計表等の既存資料の収集に際し,他課や関連機関と話し合うことができ,連携が深まりました。 |
||
| ○保健師や職員が,「健康」について幅広く捉えることができるようになりました。 ○健康づくりを「栄養・運動・休養」といった生活習慣病予防の視点から「仲間との交流や生きがいづくり」という視点への転換が必要であることが分かりました。 ○安心して暮らせるためには,「物的・社会的な環境の整備」が必要であることを実感しました。 |
||
| 調査員:全保協常務理事 山田 喜久夫 ヘルスケア総合研究所 正代 剛一 | ||
| 平成13年度 Topへ戻る |