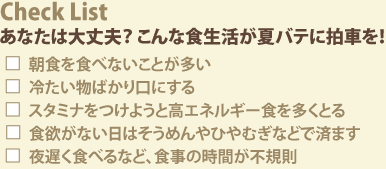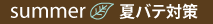 |
監修:島村トータル・ケア・クリニック院長/医学博士
島村善行 (しまむら よしゆき) 京都府立医科大学卒。国立がんセンター、千葉西総合病院などを経て 、2001年、千葉県松戸市に島村トータル・ケア・クリニックを開院。 患者の心、体、生活環境などすべての面を考えた全人的な医療を心掛け、在宅ホスピスにも精力的に取り組む。 |
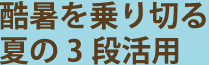 |
疲れを残さず 毎日を元気に! 熱中症予防も忘れずに!
年々、夏の暑さは過酷になるばかり。 暑いからと冷房に頼るだけの生活では、 室内外の激しい温度差に体は疲弊する一方。 実はそれが、現代人の夏バテの正体です。 そんな悪循環から脱出し、元気な体を取り戻す 疲労回復のポイントを、入浴と食事を利用した 3段活用で紹介します。
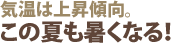
 東京の平均気温は、
東京の平均気温は、この100年で4℃近くも上昇!
年平均気温は、主要都市部を中心に上昇傾向を示しています。 中でも東京の上昇率は特に大きく、1905年の13.5℃から2004年には17.3℃に上がりました。
熱中症は気温が30℃を超えると激増するといわれています。 炎天下に出る人は、帽子や日傘で直射日光をガード!
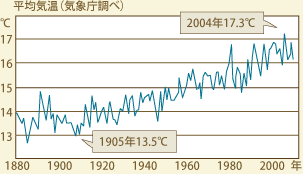
 屋外は亜熱帯 室内は寒冷地帯
屋外は亜熱帯 室内は寒冷地帯夏バテのいちばんの原因は、もちろん暑さ。 でも、それだけではありません。 暑いときほど、キンキンに冷えた飲み物をがぶ飲みしたり、冷房の効いた部屋で体を冷やしたりしていませんか? これが、夏の疲れに拍車を掛ける大きな要因の一つになっています。
冷たい水分のとり過ぎは胃腸を冷やす上、消化液を薄めるので、消化吸収力が低下して、食欲不振を招きます。 また、冷房の効いた室内で長い時間を過ごしていると、汗腺の機能が低下します。 こんな状態の体で、涼しい室内から猛暑の屋外に出ると、突然の激しい温度差に、体温を調節している自律神経も上手に対応し切れずに、 働きが乱れてきます。その結果、血圧も血糖もホルモン分泌も不安定になり、 さらなる心身の不調が続出。寝苦しい夏の夜を過ごしながら、体にも心にも疲労を蓄積させていくことになります。 現代人の夏バテの背景には、下図のような「疲れの悪循環」があります。
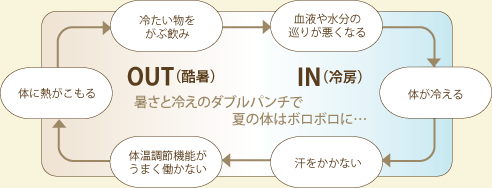
 その日の疲れは その日のうちに取る
その日の疲れは その日のうちに取る夏を元気に過ごすには、この悪循環を断ち切ること。 そのために、まず心掛けたいのは、ぬるめのお湯にゆったりとつかることです。 ぬるめのお風呂が乱れた自律神経のバランスを整え、疲れをときほぐしてくれます。 また食事では、栄養のとり方が重要なカギ。 次項から、その具体的な改善ポイントを紹介します。
 寝就きの悪い人は 早寝のための早起きを
寝就きの悪い人は 早寝のための早起きを私たちの体にある体内時計は、日光を浴びることでリズムが整い、 14〜15時間たつと眠りを誘うホルモンが分泌されます。 早起きをして朝日を浴びれば、自然に早めの時間に眠くなって寝就きも安定してきます。
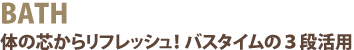
熱いシャワーで心身をシャキッ!
朝スッキリ目覚め、元気に1日をスタートするには、起床後に熱めのシャワーを浴びるのがおすすめ。 自律神経の活動モードを司る交感神経の働きが高まって、身体がシャキッと覚醒します。
ただし、あまり長い時間浴びていると発汗が起こり、体が疲れてしまうので、朝のシャワーは短時間で切り上げるのがコツです。
ぬるめのお風呂でゆったりとリラックス
夜は、朝とは逆にぬるめのお湯にゆったりと。 じっくりつかっていると、自律神経の休息モードを司る副交感神経が優位になって、心も体もリラックスしてきます。 1日の疲れが取れ、そのまま床に就けば、安眠も得やすくなります。
体内の血管は、暑さで広がったかと思えば、冷房でキュッと収縮。 この繰り返しで負担の掛かった全身を、ぬるいお風呂で休ませましょう。
シャワーマッサージで特効ツボを心地よく刺激
ツボの正確な位置がわからなくても、刺激する範囲が広いので、だいたいの位置にあてればOK。 手が届かない部分を刺激できる点がメリットです。水圧によって血行もよくなり、筋肉のこりもほぐれて一石三鳥。
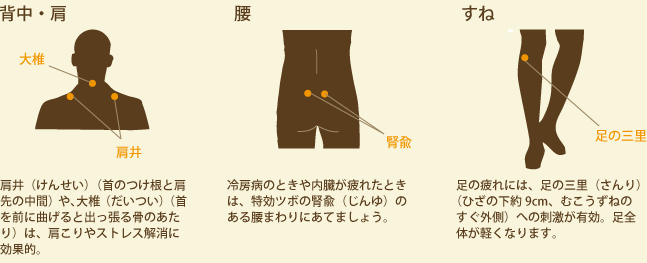

 3つの栄養素ががっちり組んで体力を維持
3つの栄養素ががっちり組んで体力を維持体力づくりの土台はやはり、バランスのよい食事から。1日3食、必要な栄養素をとることが基本ですが、 特に夏場は疲労回復やエネルギーの産生に大切な栄養素を、積極的に補いましょう。
その代表が、下に挙げた3つの栄養素。意識して組み合わせると、暑さや温度変化に対応できる体づくりに役立ちます。
特に、酢のさっぱりとした酸味や、にんにく、にら、ねぎなどの強い香味は、 食を進めてくれる名脇役。暑さで食が細くなりやすいこの時期、上手に食卓に取り入れましょう。
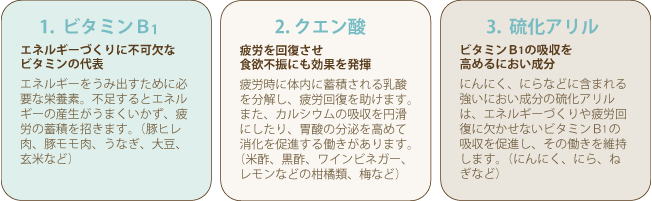
 熱中症の予防も万全に
熱中症の予防も万全に朝食は野菜と果物をしっかりと
暑い夏は、ビタミンやミネラルが汗や尿で失われやすいので、朝食のときに野菜や果物などを積極的にとりましょう。 時間がないときには、せめて1杯、野菜やフルーツのジュースを。朝の水分たっぷりの果物は、熱中症の予防にも役に立ちます。
外出時にも水分補給を忘れずに
熱中症の予防で大切なのは水分補給。スポーツドリンクならミネラルなども一緒に補給できて効果的です。 水に梅干しや少量の塩を加えてもいいでしょう。いつでも補給できるように、外出時には携帯を。